役所に申請すればもらえるお金をしっていますか?
実はあまり知られていないものも多いですが、世の中には「申請をすればもらえるお金」がたくさんあります。
しかし、ほとんどの人が知らないというものがほとんどです。
なぜならば、市役所や国も補助金は申請をすればもらえるお金を積極的に教えたりしていないからですね。
この記事では役所に申請をすればもらえるお金がわかりますので、市役所へ申請に行きお金をもらいましょう。
役所に申請すればもらえるお金一覧【簡単に戻ってくる制度を解説】
 確定申告時をはじめ、その他にも申請すれば貰うことの出来るお金が沢山あることは以外にも知られていません。
確定申告時をはじめ、その他にも申請すれば貰うことの出来るお金が沢山あることは以外にも知られていません。
そこで、申請することで貰えるお得なお金の情報をまとめてみました。
一つ一つ申請して浮いたお金は少ないかもしれませんが、こまめに申請することで、決して少なくないお金が戻ってくるのです。
戻ったお金で家族旅行へ出かけたり、マイホーム資金、教育資金にと、使い道はいくらでありますよね。
控除申請とは
税金は課税対象額に対して税率をかけて算出されます。
課税対象額、もっと簡単にいうと、税金のかかる所得というのは、給料から「給与所得控除」「色々な所得控除」を引いた額に所得によって決められた税率をかけた額を税金として収めることになるということです。
「扶養控除」や「配偶者控除」は良く知られますが、実はまだまだ、会社勤めのサラリーマンの家庭でも申請すれば課税対象額を減らし、節税することが可能な控除が以外に知られていなかったりするので、年末調整の申告書には控除対象となるものが一つでもあれば、忘れない様にしましょうね。
主な所得控除
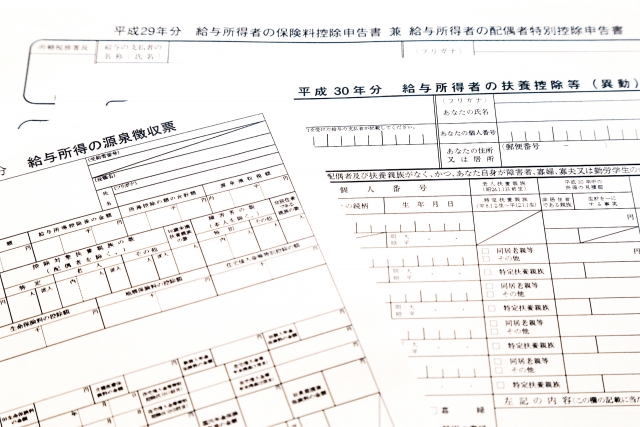
実際に、給与をもらっているサラリーマンの方が受けることが出来る主な所得控除を紹介します。
| 控除名 | 概要 |
| 雑損控除 | 災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除です。 |
| 医療費控除 | 支払いをした医療費や保険金などから10万円を引いた額が医療費控除額となります。 |
| 社会保険控除 | 社会保険料を支払った場合の控除で、その年に支払った金額が全額控除されます。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合には、最高12万円の控除を受けることができます。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合には最高5万円の控除を受けることが出来ます。 |
| 寄付金控除 | 寄付をした場合の控除で特定寄付金から2000円を引いた額が寄付金控除額となります。ただし、上限は年間所得の40%までとなります。 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合には、最高12万円の控除を受けることができます。 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合には最高5万円の控除を受けることが出来ます。 |
| 寄付金控除 | 寄付をした場合の控除で特定寄付金から2000円を引いた額が寄付金控除額となります。 ただし、上限は年間所得の40%までとなります。 |
| 寡婦・寡夫(かふ)控除 | 夫や妻と離婚や死別下場合などに受けられる控除です。 |
| 勤労学生控除 | 納税者が勤労学生の場合に受けられる控除です。 |
| 障碍者控除 | 納税者や控除対象の配偶者、扶養家族が所得税法上の障碍者にあてはまる場合に受けられる控除です。 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得金額に応じて受けることの出来る控除です。 |
| 基礎控除 | 納税者が全員一律で適用される控除です。 |
| 配偶者控除 | 配偶者の所得金額に応じて受けることの出来る控除です。 |
役所に申請すればもらえるお金一覧を紹介【簡単にもらえる・戻ってくる】
 ここからは役所に申請をすればもらえるお金一覧を紹介します。
ここからは役所に申請をすればもらえるお金一覧を紹介します。
かなりたくさんの量がありますので、気になる申請するお金がある方は目次から調べてください。
私もこの記事を書いて感じたことは「こんなに知らないお金があったんだ」というものです。
では、下記を参考にしてくださいね。
給与所得をみなおす
混乱する話なのですが、給与所得控除という言葉があります。
サラリーマンなどの給与所得者が、収入から差し引くことの出来る控除のことです。
給与所得というのは、年収から給与控除額を差し引いた額のこと、給与控除額というのは必要経費という言葉でいうと判りやすいのではないでしょうか。
実は、サラリーマンであっても、通勤費、転居費、単身赴任費など一定の支出があり、その額が給与所得控除を超えた時に、超えた部分の金額を給与所得控除に加算することが出来る制度です。
当然ですが、職務上必要性があることが条件となりますが、図書費や衣服費なども対象となるので是非活用しましょう。
ふるさと納税を利用して節税

聞いたことのある方面多いのでは無いでしょうか。
年末が近づくと、近ごろ話題となるのがふるさと納税です。
節税出来た上に、特産品まで貰えるお得な制度として、ふるさと納税を利用する方は急増中、もちろん自分自身も次は何をと楽しみながら節税しています。
仕組みは簡単で、もともと収めている地方税を、住んでいる自治体ではなく、好きな自治体に収めるというもの。対象の都道府県への寄付扱いとなるので、納税した金額から2000円を引いた金額が税金から控除されるのです。
さらに、納税先の都道府県からは、地域の特産品などを送って貰えるという、お得な制度なのです。
特産品の内容は、高級食材からパソコンに日常品まで、あらゆる物が対象になっているので、どうせ納税するのであれば、ふるさと納税を、と思うのは当たり前のことじゃないでしょうか。
扶養控除を利用
田舎の両親を「扶養」に入れることで、その分、扶養控除が認められるのです。
実際に一緒に住んでいる必要はなく、扶養人数がひとり増えると、38万円分の所得控除が認められることになります。
申請すれば貰えるお金
お役所はわざわざ教えてくれることはありませんが、申請すれば貰うことの出来るお金が実は色々あるのです。
知らないために、見逃している例は実際に多いといいます。
条件にあてはまるならば、「もらえるものは、もらっておこう」ということです。
申請すれば貰えるお金を色々と紹介します。
高額療養費
健康保険には、1ヶ月の医療費が、定められた上限を超えた場合には、超えた分は支払わなくて良いという制度があります。
上限は収入によって異なり、例えば、70歳未満で年間所得が210万円から600万円の人の場合は、1ヶ月の医療費が8万7千円を超えた金額は申請することで支払わなくて良い制度です。
出産育児一時金・出産一時金
これはよく知られた制度かと思います。支給金額は一人につき42万円です。
直接支払い制度を利用する場合には利用する医療機関の窓口で退院時に自動精算してくれます。
妊娠85日以上で、死産、流産した人も支給対象となります。
→ 妊娠から出産までの流れ一覧!出産前のお金の手続きと赤ちゃんの準備物
埋葬料
国民健康保険の加入者が亡くなった際には、家族が申請することで保険料が支払われます。加入者の家族が亡くなった際にも、家族埋葬料が支払われる制度です。
支給金額は埋葬費、家族埋葬料ともに5万円です。
民間賃貸住宅家賃助成
若い世代の定住のための促進策として、地方の過疎地域だけではなく、都心部でも家賃補助の制度が用意されている自治体が全国各地にあります。
礼金や仲介料、引っ越し手数料までも助成してくれる所もあるので、各自治体のホームページなどをチェックしましょう。
→ 分譲と賃貸の違いはなに?住宅のメリットとデメリット
犯罪被害者給付金制度
障害や殺人といった犯罪被害にあって亡くなった被害者の遺族や、怪我をした被害者が公安委員会より給付金を受け取ることができます。
金額は、被害者の年齢、収入、怪我の状況などによってことなりますが、
遺族給付金は320万円~2964.5万円
障害給付金は18~3974.4万円
重傷病給付金は上限120万円
と定められているのです。
災害弔慰金(ちょういきん)・障害見舞金
 自然災害によって亡くなった被害者の遺族には、自治体から弔慰金が支給されます。
自然災害によって亡くなった被害者の遺族には、自治体から弔慰金が支給されます。
災害が収まってから3ヶ月以上、生死不明の場合も災害弔慰金の対象となります。
災害による怪我で障害をおった人にも見舞金が支給され、請求先は各自治体となりますが、支給額は全国一律で、
生計維持者の方が死亡した場合は 500万円
その他の方が死亡した場合は 250万円
生計維持者の方が重度の障害を受けた場合は 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合には 125万円
を受け取ることが出来ます。
求職者支援制度
求職者支援制度とは、失業保険を受給できない人を対象にした、受講料無料で、3~6ヶ月の職業訓練を受けながら、月10万円の給付金プラス交通費を受け取る事の出来る制度です。
「すべての訓練実施日に出席」など、給付金を受け取ることの出来る条件は細かく設定されていますが、対象となる場合には、申請するべきでしょう。
ハローワークで説明を受けるところからスタートします。
住宅関連の給付
住宅関連の公的給付金は、申請しなければもらうことの出来ないものがほとんどです。
知っている者だけがトクをするという現実があるので、将来マイホームをと計画しているお母さんは、複数の制度を併用することも出来るこれらの制度は、機会が来た際には上手理利用しましょうね。
業者に依頼する場合の助成金など、住宅関連の助成は紹介する以外にも沢山存在するようですから、こまめに情報をチェックすることが大切です。
すまい給付金
すまい給付金は、国土交通省が行う住宅購入者を対象にした給付金です。
収入額が510万円以下の人は最大310万円、消費税が10%に上がれば収入額775万円以下の人を対象に最大50万円が給付されます。
高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は介護保険の助成制度の一つで、階段に手すりをつけたり床の段差を解消したりといった、住宅の改造をする場合に上限20万円までの助成金を受け取ることの出来る制度です。
排水設備補助金制度
自治体によって名称は違う様ですが、下水道、配管、トイレの水洗化、排水工事などを行う際に、補助金が支給される制度です。
屋外排水設備工事の限度額が10万円、浄化槽の掘り上げ撤去工事限度額が10万円など、各自治体によって微妙に違うそうです。
緑化推進事業補助金
生け垣を作ったり、樹木を植えたり、屋上ベランダや壁面を草花で彩ったりすることで補助金が支給されます。
整備にかかった費用の二分の一、支給上限は10万円というのが大阪市の例で、この制度もまた、自治体によって色々ある様です。
住宅ローン控除
住宅ローンを利用している人は、税金の控除を受けることが出来ます。
その金額は住宅ローン借り入れ残高の1%です。
10年以上の住宅ローンを利用していることが条件となり、以前は2000万円だった最大金額が、増額されて今は4000万円となりました。
住宅リフォーム補助
地方公共団体が実施している補助金のひとつで、最大10万円ほどの補助を受けることが出来ます。
申請前に工事に入ってしまうと、補助が受けられなくなってしまうこともあるそうなので、注意が必要です。
太陽光発電補助
 太陽光発電はエコだけではなく、自家発電の電気はもちろん自家消費することで電気代が安くなり、更には余った電気は電力会社が買い取ってくれるのです。
太陽光発電はエコだけではなく、自家発電の電気はもちろん自家消費することで電気代が安くなり、更には余った電気は電力会社が買い取ってくれるのです。
1キロワット当たり37円ほどで買い取ってくれるそうなので、長い目で見ると十分もとは取れると、導入する家庭は増えているとのこと。
太陽光発電を導入するには、工事費など、結構な費用がかかるのですが、各都道府県が太陽光発電の導入工事への補助金を、20万ほど支給されるので、利用しない手はありませんね。
家族関連の給付
お母さんにとって、身近な給付金を纏めてみました。
結婚祝い金
主に人口が減少している市町村では、人口増加推進策として行っている制度で、結婚してその市町村に一定期間すむことで5万~10万円の祝い金を貰えるのです。
中には、海外から配偶者を迎えて6ヶ月以上定住すると、100万円も支給される例もあるようですね。
ご自身が暮らす市町村にこれらの制度がないか、要チェックです。
出産祝い金
健康保険からも「出産育児一時金・出産一時金」が支給されますが、それとは別に、お住いの自治体から支給される祝い金もあります。
不妊治療助成金
不妊治療は経済的な負担も大きく、厚生労働省は自治体の指定を受けた医療機関での特定の治療に助成金を支給しています。
夫婦の所得が730万円未満であり年齢によって助成を受ける事の出来る回数も異なります。
私立幼稚園就園補助金
子供が私立幼稚園に通う家庭の経済的負担を軽減するために、自治体が支給しているのが、この私立幼稚園就園補助金です。
この補助金もまた、世帯収入や幼稚園に通う子供の人数によって異なります。
失業給付金(基本手当)
失業給付金(基本手当)、いわゆる失業手当は離職時の年齢によって適用される割合が違い、賃金日額が高いほど給付率は低くなり支給額の上限もあります。
低所得の人が、より手厚いサポートを受けることが出来る制度だといっても良いでしょう。
失業給付金を受ける条件は、離職前の2年間に保険期間が通算12ヶ月以上あること、さらに働く意志があって就職出来る能力もありながら職につくことができない状態にあること、など受給条件が幾つもあります。
怪我や病気、出産を控えていたり退職してから留学の予定がある人などは失業給付金を受給することはできないのです。
支給される基本手当は、離職直前の6ヶ月間の供与の合計を180日で割った金額の5~8割となります。
求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険に加入していない個人事業主、加入期間が短くて受給資格に満たない方、就職が決まらないまま、学校を卒業したなど、失業給付金を受給出来ない人が対象となる制度です。
支給条件は世帯全体の収入が「月25万円以下」、「金融資産が300万円以下」、「欠席せずに訓練を受けたこと」など細かく定められています。
とは言え、無料で職業訓練を受けることが出来たり、通学のための交通費なども支給されますし、条件さえ満たしていれば、月に10万円の支給もあります。
延長給付措置
支給金額や給付日数が決まっても以下に紹介する条件に当てはまれば、給付日数が1ヶ月以上も延長されることがあります。
「個別延長給付」と呼ばれる制度で、例えば、後1回求人応募することで条件を満たすことも実際にありますから、雇用保険を最大限利用するのであれば、これらのことも知っておくことは少しでも多くの給付金を貰うためには、大切なことだと思うのです。
個別延長給付
◆安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返している45歳未満の人。
◆雇用機会の少ない地域に住んでいる人
◆職業安定所が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた人
解雇や倒産、契約期間更新がされなかった人などを対象に、失業保険を60日間も伸ばすことが出来たのです。
出来た、と過去形なのは、この制度は平成29年3月に一旦廃止され、平成29年4月からは恒久的に個別延長給付を実施することとなったものの、従来のものよりは大幅に対象条件が狭まってしまっています。
◆「難治性疾患」「発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者」「障害者雇用促進法第2条第1号に規定する障害者」いずれかに該当する方
◆激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた方、または激甚災害法の指定地域に居住している方
◆激甚災害その他災害救助法の適用となる災害で離職を余儀なくされた方
激甚災害というのは、大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害のことを指します。
さらに、「積極的な求職活動」が求められます。これは、ハローワークに「指導基準に照らして職業指導を行うのが適当である」と認めてもらうことが必要で、簡単にいうと、企業へ応募した回数が必要となるのです。
回数が増えるほどに、給付日数も延長されるということですね。
技能習得手当
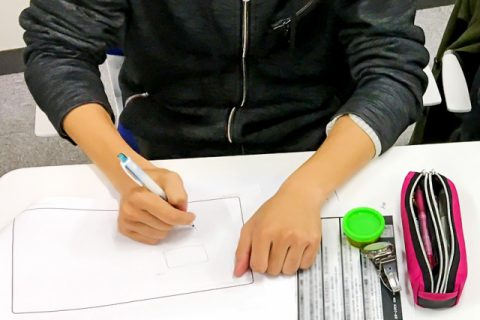 ハローワークが実施している求職者向け公共職業訓練など、特定の職業訓練を受けている期間は、日額500円が支給されます。加えて交通費まで、上限42500円までが支給されるのです。
ハローワークが実施している求職者向け公共職業訓練など、特定の職業訓練を受けている期間は、日額500円が支給されます。加えて交通費まで、上限42500円までが支給されるのです。
その他、もの作りを中心とした訓練、たとえば、金属加工や電気設備といった特定の職業訓練を受けると、日額2000円にもなるそうです。
この間は、基本手当も所定通り支給されるため、前向きに再就職を考える際には、とても有効な制度だと思いますよ。
再就職後にもらえる手当
雇用保険の期間終了前に、就職先が決まった場合に支給されるのが、通称「お祝い金」です。再就職先の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、再就職手当に加えて国が差額を補ってくれる手当があります。
就業促進定着手当がそれで、離職前の賃金日額から再就職先の賃金日額を引いた金額の6ヶ月分が支給されます。
傷病手当金
健康保険に加入している会社員が、業務外の怪我や病気で長期間仕事を休まなければならない時に支給されるのが傷病手当金です。
支給額は1日に付き、標準報酬日額の三分の二、標準報酬日額は直近三ヶ月の給与平均額の三十分の一で計算されます。
この傷病手当金は、申請しなければ受給出来ないので、該当する場合は書類の準備などをして、直ぐに手続きをはじめることです。
介護休業給付金
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者は、職場復帰を前提として、家族を介護するために休業した場合には、介護休業給付金を受け取ることが出来るのです。
要介護状態にある対象家族、一人につき一回、連続する3ヶ月を限度に支給されます。
介護休業給付金の支給額は、休業前6ヶ月の給与を180で割った休業開始時賃金日額に支給日数をかけた額の40%が目安となります。
事業主は、労働者が介護休業の申し出や介護休業給付金を受け取ったことでは介護や言及は出来ないという法律があるので、上手に利用したい給付金の一つだと思います。
教育訓練給付制度
社会人としてのキャリアアップのために各種の講座などを受講すると、国からの給付金があるのです。受講費用の40%、年間最大32万円までの給付を受けることができます。
利用できるのは、通算2年以上の加入歴のある雇用保険の被保険者と以前加入していた離職者という条件があります。
付加年金
毎月の国民年金に400円上乗せして支払うだけで、将来受け取れる年金の額がアップするのです。
付加年金の給付は一生続くので2年間年金を受け取ったらもとが取れる計算になるので、老後の資金として400円を投資したいと思います。
生ゴミ処理機導入

一般家庭から出る、燃えるゴミの約半数は生ゴミなのだそう。
増え続けるごみ問題の解決策として、各自治体は生ゴミリサイクルに協力する家庭にたいして、補助金を出しているのです。
色々な生ゴミ処理機がありますが、最大で2~3万円ほどの補助金を出している自治体が多いそうです。
生ゴミを肥料にリサイクルしてガーデニングや家庭菜園にと活用出来るというのは、ちょっと考えただけでも楽しくなってきませんか?
申請方は自治体によって違い、購入店が指定されていたりすることもあるので、まずは自分が住んでいる自治体の詳細を確認するようにしましょう。
自立支援制度
現代病の一つとして数えられるうつ病ですが、通院が必要になった際に、医療費を一割にすることが出来るのが自立支援制度です。
通常の保険適用を受けた際には、自己負担金が三割ですから、これが3分の1になるというので、金額は少なくありません。
アルコール依存症やその他の精神疾患にも対応しているのでもしもの場合には大いに利用するべきです。
役所に申請をすればもらえるお金に該当したらどうする?【簡単な手続き】
 ここでたくさんの申請すればもらえるお金を紹介してきました。
ここでたくさんの申請すればもらえるお金を紹介してきました。
基本は役所へ手続きに行くことでもらえるお金となっています。
何よりも申請をすればもらえるお金があるのに申請をしないのはもったいないですよ。
わからなければ問い合わせをしよう
ここで紹介をしたようなお金というのはあまり表には紹介をされないようなことばかりとなっています。
申請をしてお金をもらう。
文字で書くと簡単そうに思えますが、実は手続きがとても面倒でやり方も複雑でとても扱いにくいと言われているお金となっています。
そこで「面倒くさい」と思ってしまうとなかなか手にすることは難しくなってしまいますのでそこを乗り切ることが大事。
もしわからなければ役所に問い合わせをして申請の方法を確認してみましょう。
自治体によっても異なるもらえるお金
役所も最初から「こんなお金がもらえますよ」とは教えてくれませんが、「こんなお金を申請したいのですが、方法を教えて」というよに行ってみると普通に教えてくれます。
もちろん全国の自治体対応のものがほとんどですので、もらうようにしましょう。
また、自治体によって金額が異なる場合もあります。
例えば、出産祝い金のなうと数万円程度のところが多いのですが、北海道の福島町に生まれるとと第三子は100万円となっており内訳は町内の商品券が30%となっており、3年間の分割です。
こんな風にいろいろと自治体によってもことなりますので、わからない時、こんな補助金はないのか知りたい時にはまず自治体の市役所へ問い合わせをしてみましょう。
役所の申請すればもらえるお金一覧のまとめ【お得にもらおう】
 実は、紹介したものだけではなく、更にたくさんの「申請すれば貰えるお金」の制度はあるということに、今回、改めて気が付きました。
実は、紹介したものだけではなく、更にたくさんの「申請すれば貰えるお金」の制度はあるということに、今回、改めて気が付きました。
補助金などを支給してくれる、役所や自治体は進んでそれらを教えてくれることはありませんので「知らないで損」という方は本当に多いのではないでしょうか。
手続きが面倒なものも多いかもしれませんが、お金が戻ってくると思えば全く苦にならないんじゃないでしょうか?
ここに紹介をした申請をするお金なのですが、実際には市役所などでも教えてくれるものではなく基本的には自分で申請をしなければもらうことができないお金となっています。
申請をすればもらえるお金なので、せっかくここで情報を仕入れたのですからお金を手に入れてくださいね。
人気記事 → 保育士の結婚年齢の平均は?相手の選び方とできない時の対処法
人気記事 → 子供の身長を伸ばす方法4選とサプリを紹介!年齢別の平均目安と遺伝

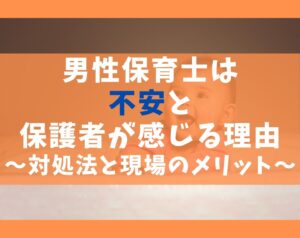
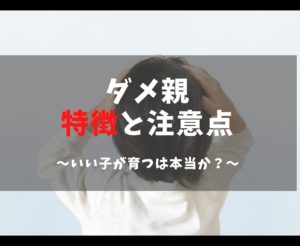






コメント
コメント一覧 (14件)
[…] 関連記事→お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]
[…] 関連記事→お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]
[…] 合わせて読みたい記事→お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]
[…] そんな申請をしてもらえるお金について「お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧」に書いていますので参考にしてみてください。 […]
[…] 役所からもらえるお金に関しては「お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧」に書いていますので参考にしてください。 […]
[…] 2018.09.04児童手当は貯金が基本?使い道と支給をされる金額 申請方法について 内閣府の意向により異なる児童手当の金額 児童手当と聞くと、子育て世代にとっては非常にありがたいものです。 毎月一定の年齢の子供を持っている家庭に国からお金が支給をされるというものになっているのですが、その使い道を… 関連記事 お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]
[…] 2018.10.09子育てはお金がかかる?子供とお金に関する情報のまとめ お金がかかる子育ての現実 私も娘2人を育てていますが、子育てって思っている以上にお金のかかるものだなというのが印象です。 もちろん一人の子供を育てるのに約2000万円かかるといわていますが他にもイレギュラーなもの…合わせて読みたい記事お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]
[…] 2017.12.27お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 役所も秘密にしている国からもらえるお金とは? お金がほしいとは誰もが思っている気持ちなのですが、そんなに簡単には手に入らないものです。 普通は一生懸命仕事をして、その対価とお金をもらうという方法になりますよね。 … […]
[…] 2017.12.27お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 役所も秘密にしている国からもらえるお金とは? お金がほしいとは誰もが思っている気持ちなのですが、そんなに簡単には手に入らないものです。 普通は一生懸命仕事をして、その対価とお金をもらうという方法になりますよね。 … […]
[…] 2017.12.27お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 役所も秘密にしている国からもらえるお金とは? お金がほしいとは誰もが思っている気持ちなのですが、そんなに簡単には手に入らないものです。 普通は一生懸命仕事をして、その対価とお金をもらうという方法になりますよね。 … […]
[…] → 役所に申請すればもらえる戻ってくるお金一覧!お金がほしい人必見 […]
[…] また、市役所などからもらえるお金は出産以外にもいろいろとありますので役所に申請すればもらえるお金一覧!戻ってくるお金もチェックも一緒にチェックしておきましょう。 […]
[…] 2018年 8月 07日 トラックバック:お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 … […]
[…] → お金がほしい人は必見!役所も教えない申請すれば貰えるお金の情報一覧 […]