保育士資格試験は難しいです。
実は保育士になりたい人が資格を取得するための受ける資格試験で合格を勝ち取るためには難関だと言われている試験です。
なぜならば、9教科の試験にすべて合格をしなければならず試験の範囲も広いため勉強をしたとしても一筋縄ではいかないですし、一発合格は本当に少ない現実があります。
試験の日程を頭にいれて資格取得を目指して取り組んでいく必要がありますね。
この記事では保育士試験について書いています。
保育士資格の一発合格率は3%と言われる理由【難関と呼ばれる試験】
 保育士の資格の合格率について書いていきましょう。
保育士の資格の合格率について書いていきましょう。
保育士の合格率について言われているのは約20%の人しか合格をしないといわれています。
こんなにも難しい保育士試験……。
そりゃ保育士減るし虐待する保育士も出てくるよなぁ……。地味に昭和レトロ時代の近所のおばちゃんとか無資格で使えないのかね??介護士も含めて…… https://t.co/EfOp4QYhJ5— 熊太郎@超公式💙 (@hayashi_1229) December 20, 2022
詳細な情報を見てましょう。
| ・平成25年度:17.4%
・平成26年度:19.3% ・平成27年度:22.8% ・平成28年度:25.8% ・平成29年度:21.60% ・平成30年度:19.74% (参考記事:厚生労働省「保育士試験実施状況」) |
このようになっており、ここ数年の平均としては約2割しか合格をしない現況がありますね。
平成28年から合格率が上がっている理由としては、待機児童問題、潜在保育士の職場復帰が見込めない理由から保育士の資格試験が2回になっているためですね。
保育士合格率が低い理由
合格率については筆記試験がとにかく低くなっており、平成28年度の合格実績をみてみると筆記試験25.2%、実技試験89.1%、合計22.8%となっています。
つまり、筆記試験に合格をすれば保育士の資格試験への合格の道も見えてくるのですが、そこまでたどりつかない方も多くなっていますね。
合格率が低く見える理由は保育士資格試験の科目数という理由があります。
保育士の筆記試験は全部で9教科合格しなければなりません。
そのため、合格をしている20%は9教科をすべて合格した人の数値を指していますので低く見える仕組みがあります。
一発合格率は3%!9教科の合格は難しい【3年間有効】
保育士の資格試験は合格をするとその先3年間有効となります。
そのため、2年目からは不合格であった試験のみを受ければよいということになります。
例えば、1年目に3教科合格、2年目に4教科合格、3年目に2教科合格をすれば全部で9教科なので3年目にして合格となります。
この場合は1年目の合格がぎりぎり適用となるので合格となりますが、もし3年目に1教科を不合格していれば1年目の3教科を4年目に再受験をしなければなりません。
そのような理由から保育士の資格試験の合格率は低くなっていますね。
一発合格はかなり厳しいといえますね。
もちろん、一発合格をしている人もいますが、割合としては3~5%です。
これを高いととるか、低いと取るかはあなた次第ですね。
不合格になりやすい教科
中でも不合格になりやすい教科が「社会的養護」「教育原理」「社会福祉」となっています。
特に多いのが3年目にこのいずれが不合格になり、結果的に1年目の試験と受け直すということになる人もいますので注意をしましょう。
この3教科がとても重要なので、計画的に保育士資格試験の受験対策をしていきましょう。
他にも神奈川県、大阪府、沖縄県、千葉県の4府県において地域限定保育士試験を実施することになっていますのでその地域に住んでいる人ならば資格の取得を検討してください。
試験に合格をした後を考えよう
保育士資格を取得をしたい人も多いですが、はやり付け焼刃で通過をするような資格試験ではなく難易度は結構高いのでそこは注意をする必要があります。
試験勉強は継続をして知識にしていくことで合格の道も見えてきますのでそのためにも資格を取得した後の自分の姿や希望をイメージしましょう。
また、資格を取得して保育士として働く場合には新人の先生と同じ扱いになりますので就職先は保育士紹介型のエージェントを利用するととても便利ですよ。
保育士資格試験とは?保育士の仕事と働ける場を解説
 もちろん保育士試験を受けるということは資格を取得することになりますので、念のため保育士とは?というところからおさらいをしていきましょう。
もちろん保育士試験を受けるということは資格を取得することになりますので、念のため保育士とは?というところからおさらいをしていきましょう。
保育士は近年少子高齢化社会の中で地域の子育ての中核を担う専門職として保育士のニーズは年々高まっています。
このような社会情勢を背景として、2003年(平成15年)11月29日の児童福祉法の一部改正施行により保育士資格は法令化され国家資格となりました。
登録をするには、各都道府県の知事に委託をしており、保育士登録機関登録事務センターで行われます。
保育士の定義ですが、「児童福祉法第18条の6」
1,都道府県知事の指定をする保育士を養成する学校その他の施設(指定保育養成施設)を卒業したもの。
2,保育士試験に合格をしたもの。
このように定められていますね。
(参考:ウィキペディア「保育士とは?」)
保育士の仕事
保育士は保育所をはじめとする「児童福祉法」で定められている12種の児童福祉施設のうち主に10施設において、保育の専門家として子どもたちが心身共に健康に育ち、社会に適応できるように児童の育成にかかわると定義をさてています。
さらに詳細な定義を見てみると、児童福祉法18条の4保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門知識及び技術をもって、児童の保育および児童の保護者に対す保育に関する指導を行うことを業とする者を言います。
ちなみに、児童福祉法に定められている12種類の福祉施設は以下となります。
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設(母子支援員として)
・児童厚生施設(児童の遊びを指導する者として)
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設(児童生活支援員として)
・児童家庭支援センター
※赤字は保育士が働くことのできない児童福祉施設となっています。
保育士資格を持っている人のほとんどは保育園で保育士として働いている人がいますが、私の知り合いは児童養護施設や障がい者の作業所などが多くなっています。
保育士資格試験とは?
保育士試験とはその名前の通り国家資格である保育士資格を取得するための試験となっており、昨今保育士不足で問題となっているのですが、社会人になり保育士を目指す方も多いです。
保育士の資格を取得するためには短期大学、専門学校、大学などへ入学をして実習へいき、単位を取得し卒業をすれば取得が可能となりますし、保育士の資格試験に合格をすれば資格の取得が可能です。
大学などへ進学をすれば取得は近いですが、最低でも2年は通わなければなりません。
それに比べて資格試験は最短数か月で取得も可能ですし、費用がかからないメリットもありますので試験に臨む方は多いです。
特に社会人の人は独学で勉強し試験の望む人が多いです。
→ 保育士の専門学校の学費相場はいくら?2年制養成の流れと進路
保育士の仕事内容の難しさ
私も保育士をしてきて本当に楽しかった思い出が多いです。
もちろん低賃金で、過剰労働の辛さというものはあるのですがそれでも保育士資格を目指しているということは保育士という仕事を目指しているのだと思いますね。
保育士は子供の笑顔の触れられるのはもちろんなのですがそれよりも目の前で子どもが成長をしていく姿を見れるというのはとてもメリットの高いものだと思います。
また、保育士をしていて何よりも感じるのは毎日「ありがとうございます」と言ってもらえる仕事ってそんなにないなと思いますね。
毎日仕事にいっているお父さん、お母さんの代わりに子供を見ることになりその子供の世話をして成長の礎になれる仕事ってなかなかないですし、それに感謝をしてもらえることの仕事です。
本当に毎日「ありがとうございます」と言ってもらえる仕事なんてあまりないので保育士になる夢を見て資格試験合格へ向けて頑張っていきましょう。
保育士試験の受験資格と日程と受験者数【一発合格の少なさに驚く】
 では、本題の保育士の受験資格について書いていきましょう。
では、本題の保育士の受験資格について書いていきましょう。
試験に合格をすれば誰でも保育士になれるのですが、基準を最低限クリアしておかなければなりませんので理解をしておきましょう。
1,大学に2年以上在学をしており、62単位以上取得をしたもの
2,大学に1年以上在学をしており、年度中に62単位以上習得をする見込みのあるもの
3,短期大学・高校専門学校・専修学校専門過程または各種の学校・高等学校及び中等教育学校後期課程の専攻科・特別支援学校専攻科を卒業した者(見込みを含む)
4,平成3年3月31日までに高校を卒業した者
5,平成8年3月31日までに高校保育科を卒業した者
6,上記3,4以外のもので高校もしくは中等教育学校卒業後、児童福祉施設等で2年以上、総勤務時間2,880時間以上の実務経験がある者
7,児童福祉施設等で5年以上、総勤務時間数7,200時間以上の実務経験がある者
8,都道府県知事が受験資格をあると判断したもの
このように定められていますね。
保育士資格試験と日程について
平成16年試験より「保育士試験事務センター」がすべて都道府県の指定試験機関として保育士試験を実施しています。
受験希望者は受験申請書に希望をする受験申請地などを記入し、所定の期間内に保育士試験事務センターへ申請をします。
試験は原則年1回の実施となっていましたが、平成28年から年2回おこなわれるようになりました。
試験は各都道府県の主催で行われていますが、それぞれの選定会場で実施をされます。
保育士試験の実施方法
保育士試験は大きく分けて2つの試験が実施をされることとなります。
1つめは筆記試験で2つめは実技試験となります。
1次試験が筆記試験となっており、筆記試験に合格をした人のみ実技試験を受けることができ、実技試験も合格をすることにより保育士資格を取得することができます。
合格基準は各科目によって異なるのですが、満点の60%以上の得点をしておかなければならないためかなり狭き門といえる試験です。
ちなみに幼稚園教諭を持っている人ならば平成25年より「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」が試験免除科目となっています。
過去の受験者数と合格率
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 平成24年 | 52,257名 | 9,726名 | 18.6% |
| 平成25年 | 51,055名 | 8,905名 | 17.4% |
| 平成26年 | 51,257名 | 9,894名 | 19.3% |
| 平成27年 | 46,487名 | 10,578名 | 22.8% |
| 平成28年 | 70,710名 | 18,229名 | 25.8% |
保育士の試験の難易度としてはかなり難しいと言われています。
後ほど紹介をしますが、試験内容が多岐にわたることから1年で独学で合格をしようと思った場合には相当な努力が必要になります。
教科数は9教科で3年以内にすべての教科をクリアすれば合格となります。
もし3年かけて独学で保育士資格を取得しようと考えているならば、保育士養成学校へ行くほうが確実に取得も可能となりますね。
私の知人は保育士試験を独学で受けていました。
過去問を見ながら勉強をしていたようで、試験を終えて速報をみた時点でなんとか3年かけて合格をしていたとのことです。
この人は相当勉強をしていたので、甘い気持ちで保育士資格ほしいな~という程度では正直難しい可能性もありますね。
結果は自己採点でもすぐにわかりますし、もちろん試験後に自宅へ結果が郵送をされてくることとなります。
→ 保育士受験資格は実務経験と年齢がポイント!通信教育で取得できる?
地域限定保育士試験
地域限定保育士も本来の保育士試験と同時に行われることになりました。
これは大阪府が独自に行っている試験となっているのですが、
通常試験の受験者で筆記試験の全科目合格者は従来の実技試験を行います。地域限定保育士試験の受験者で筆記試験の全科目合格者は、保育実技講習会(5日程度)を受講していただきます。
(引用:大阪府「平成30年後期保育士試験」
地域限定保育士とは、平成27年通常国会で成立した「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」において、「国家戦略特別区域限定保育士」(地域限定保育士)となるための試験制度が新たに創設されました。
地域限定保育士試験合格者は登録後3年間、試験を受け資格を取得した自治体内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができます。
つまり保育士試験にはもちろん合格をしなければなりませんが合格後に大阪で働くことにより3年後には地域限定から通常の保育士資格を手に入れられる制度です。
※地域限定保育士試験は大阪府以外に住所を有する方でも受験が可能です。
※試験範囲及び内容(筆記)については通常試験から変更ありません。
保育士資格試験の筆記試験の内容【一発合格が一番難しい】
 保育士資格試験の内容は以下の表にまとめており、詳細については表の下に書いていますので参考にしてください。
保育士資格試験の内容は以下の表にまとめており、詳細については表の下に書いていますので参考にしてください。
Twitterを始めて知った事の中に
「独学で保育士資格を取得している人が想像以上に多い」というのがある
私も数十年前資格取得の際に独学を検討したけど実習などが難しいと判断し専門へ進んだ
社会人経験のある人や子育て落ち着いたママさん達ってすごく保育士を目指すのすごくいいと思う
— 毒舌うさぎ@保育士のあれこれ (@hiyoko_hoiku) October 18, 2022
| 試験科目 | 出題数 | 配点 | 時間 |
| 保育の心理学 | 20問 | 100 | 60分 |
| 保育原理 | 20問 | 100 | 60分 |
| 児童家庭福祉 | 20問 | 100 | 60分 |
| 社会福祉 | 20問 | 100 | 60分 |
| 教育原理 | 10問 | 50 | 30分 |
| 社会的養護 | 10問 | 50 | 30分 |
| 子どもの保健 | 20問 | 100 | 60分 |
| 子どもの食と栄養 | 20問 | 100 | 60分 |
| 保育実習理論 | 20問 | 100 | 60分 |
※筆記試験は五指択一式のマークシート形式となっています。
1.保育の心理学
・身体、運動、認知、社会の各領域における子どもの発達過程および特性や、エリクソン、ピアジェなどの代表的な心理学者の理論を抑えておきましょう。
・発達障害などに関する具体的な保育方法を問う問題も増えています。
2.保育原理
・保育の社会的役割や法制度、保育の歴史、日本や世界の保育に関する思想家について抑えておきましょう。
・保育所保育指針からの出題や保育所保育指針を踏まえた実際の保育にかんする事例問題も多く出題をされます。
3.児童家庭福祉
・児童家庭福祉の歴史、児童福祉施設んの種類や対象、児童福祉法など関連法令の目的や定義、理念などを理解しましょう。
・子育て支援、母子保健、障害児福祉や児童虐待防止、少年非行などついても出題をされます。
4.社会福祉
・社会福祉の理念に関する用語と意味、諸外国の社会福祉の歴史、主な社会福祉機関、社会福祉法などの関連法令を学びましょう。
・生活保護、年金制度、保険給付、地域福祉などについても出題をされます。
・相談援助や保育士の対応などについての事例問題も多く出題をされています。
5.教育原理
・教育基本法や学校教育法などの教育関連法、国内外の教育思想家については毎年出題をされています。
教育の歴史的変革や教育評価、現代教育の諸問題、キャリア教育など多角的な視点から学習をし、教育動向の把握に努めてください。
6.社会的養護
・社会的養護の現状について出題をされます。施設養護(家庭的養護含む)と家庭養護の制度体系を抑えておきましょう。
・児童福祉施設の職員配置とその役割、設備基準も確認しておきましょう。
7.子どもの保健
・子どもの発育、発達、感染症を含む安全衛生管理、母子保健の理解が必要です。
・人口動態統計についても毎年出題をされています。出生数などの動向や死因順位などを確認しておきましょう。
8.子どもの食と栄養
・栄養に関する基礎知識、食育、病気、障害のある子ども食生活などを学びます。
・食生活指針、日本人の食事摂取基準、授乳と離乳の支援ガイド、国民健康・栄養調査、学校給食などについて多く出題をされています。
9.保育実習理論
・伴奏和音、音階、調、和音を学習し、移調やコードネームのポイントは鍵盤の位置を確認しながら理解をしましょう。
・表現の発達段階や造形材料や技法、彩色などを学習し、絵本作家の名前や特徴的な絵の表現方法も押さえておきましょう。
・保育所保育指針の表現や言葉、地域に開かれた子育て支援や職員の資質の向上などについてしっかりと確認をし、児童福祉施設の職員配置などをしっかりと覚えておきましょう。
保育士資格試験の実技試験内容【ここまでくれば一発合格も可能】
 実技試験は筆記試験後に実施をされることとなります。
実技試験は筆記試験後に実施をされることとなります。
指定をされた3分野のうちの2分野を選択して受験をすることになります。
| 分野 | 配点 | 試験概要 |
| 音楽表現に関する技術 | 50 | 課題曲についてピアノなどの指定の楽器で伴奏しながら歌う |
| 造形表現に関する技術 | 50 | 指定課題について絵を描く |
| 言語表現に関する技術 | 50 | 指定をされた童話などを3分間口演する |
→ 保育士資格実技試験の造形 言語 音楽の試験内容と対策!合格率と服装
試験の免除について
・前年度もしくは前々年度に保育士資格試験の一部の科目を合格している人はその科目が免除されます。
・幼稚園教諭免許所有者で厚生労働大臣が指定する保育士を養成する学校そのほかの施設において指定をされた科目を履修した人はその科目が免除されます。
・幼稚園教諭免許所有者の免除科目に関しては平成25年度より、「保育心理学」「教育原理」実技試験が免除となります。
平成30年の試験より社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格保持者は社会福祉、児童家庭福祉、社会的養護の3科目が免除とないます。
当日の持ち物について
保育士試験を受けるとなった場合には持ち物が大事です。
もちろん受験業にも記載をされているのですが、忘れないように、間違えないように気を付けましょう。
| ・受験票 ・HB~Bの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム ・腕時計 |
詳細な情報についても書いていきましょう。
受験票がなければ試験を受けることができませんので必ず持参をするようにしましょう。
万が一受験票を紛失した場合には、至急保育士試験事務センターへ連絡をしてください。
筆記用具も重要
鉛筆も大事です。
鉛筆もしくはシャープペンシル以外で記入は0点になる場合がありますので気を付けましょう。
その際に机の上に筆箱を置くことは禁止となっています。
ただし、鉛筆削りの持ち込みは会場ないに可能となっていますが、もし試験中に利用をするとなった場合には試験監査員の了解を得てから使用をしてください。
腕時計に関しては、試験室に時計がない場合があるため持参をすべきとなっています。
指定があり、アラーム音がないもの、計算機や電話機能のついていないもの、置時計は不可となっています。
もちろん携帯電話の持ち込みは不可となっており、操作方法を事前に調べて電源を切るようにしましょう。
もちろん携帯電話の機器を時計として使用することは禁止をされています。
服装はどんなのが良い?
保育士資格試験の当日の服装について悩む人もいると思いますが、服装のついては自由となっています。
そのため、着慣れないスーツを着る必要もありませんしかしこまった服装ではなくても大丈夫です。
中には個性的な服装をしている人もいるようですが、試験会場では特に問題はありません。
ただし、これは筆記試験に関してのこととなっており実技試験に関しては面接官と面接をしたりすることとなるため服装には気を付けましょう。
保育士資格試験の一発合格率と試験内容のまとめ【継続して受けよう】
 保育士資格試験についていろいろと書いてきましたが、なかなか簡単には通過をすることが難しい試験であるというのが正直な印象ですね。
保育士資格試験についていろいろと書いてきましたが、なかなか簡単には通過をすることが難しい試験であるというのが正直な印象ですね。
もちろん毎年受ける方は増えていますし、最近は社会人をしてから保育士になりたいと思っている人も多く社会人経験者で全く違う仕事をしてきた人がいきなり保育士になってくるケースも多いです。
学校を卒業して保育士になった人、社会人で保育士になりたいとおもって保育士になった人など一緒に働いてきましたが保育士として仕事をしていく中では保育士資格試験に合格をしてきた人の方が人材的にはすごく良い人も多いです。
資格を取得すれば保育士として働けますので勉強頑張っていきましょう。
人気記事 → 保育士転職サイトランキング!おすすめ22社を徹底比較【口コミ評判】
人気記事 → 保育士バンクは最悪って本当?元保育士が全て暴露【登録した体験談】
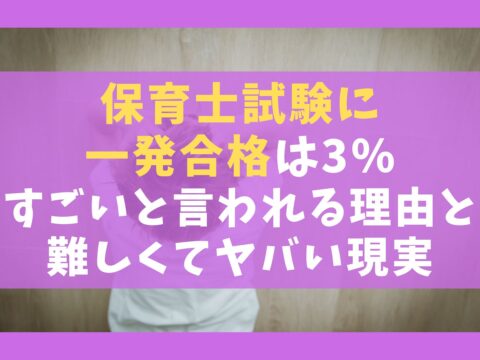
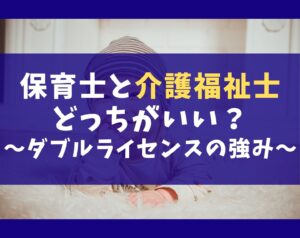
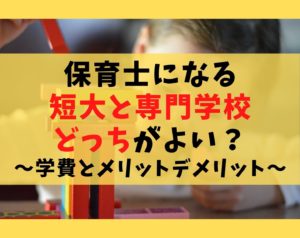



コメント