企業主導型保育事業のデメリットをしっていますか?
保育園には形態があります。
認可保育園、無認可保育園、認証保育園、ベビーホテルなどいろいろと聞くことが多いですが、最近増えている形態の保育園といえば「企業主導型保育園」です。
なんか企業がやっている保育園なの?と思っている方も多いのですが、この保育園は世の中にある保育園とは違った形の保育園と言われています。
この企業主導型保育園は補助金や助成金をもらって保育園を作れるという点で参入をしてくる企業も多いのですね
この記事では企業主導型保育園について書いています。
記事を読みえ終えることで企業主導型保育字魚のデメリットや増えている理由がわかります。
企業主導型保育事業のデメリットとは?助成金で保育園を作る問題点

まずは企業主導型保育事業について書いていきます。
内閣府のHPを見てみると、こんなことが書いてあります。
1 事業の目的
本事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
また、政府は待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿の整備目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分としましたが、本事業の創設により、一層の保育の受け皿整備を行っていきます。
2 事業の特徴
働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。
(延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能)
複数の企業が共同で設置することができます。他企業との共同利用や地域住民の子供の受け入れができます。運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
引用:内閣府HP(企業主導型保育事業の概要)
2016年に内閣府がスタートした現在保育施策の中核を担うような存在となっています。
企業主導型保育施設の事業目的と特徴
企業主導型保育施設とは、子ども・子育て支援法を改正し2016年6月に閣議決定をされた「ニッポン1億総活躍プラン」により、内閣府が主体となって、
これまでに事業主処出金を0.15%から0.25%に引き上げる財源確保により実施される企業内保育の事業となります。
目的な多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所の待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資するという点です。
特徴としては内閣府のHPにこのように書いてあります。
・多様な就労形態に対応した保育サービスの提供が可能
・地域枠の設定が自由(利用定員の50%以内)
・運営費、施設整備費のついて認可施設並み助成が受けられるため保育料を認可並みに設定が可能
・複数企業による共同設置、利用が可能
・企業主導型保育事業の特色・メリットを活かした事業展開を図ることができる
要するに認可を必要とせず、かつ企業の推進力や資金力を活用し、企業内保育園を前提に、従業員の採用や定着に活用しながら手厚いに助成金をもとに、安定運営を実現させることで待機児童の解消に役立てるということです。
助成金はいくら?企業主導型の保育園の構造を解説
内閣府が公表をしている女性要綱にも記載されていますが、施設型給付や地域型給付事業同様に、地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士比率区分の5つの区分における基準額を基礎として助成額を算出します。
2017年時点の公定価格で算出をすると、例えば東京都の定員20名の保育所を運営する場合、保育士比率100%、1日11時間開所、週7日未満開所の場合、基礎分単価で年間4000万円を超えます。
加えて、延長保育加算、夜間保育加算、賃貸料加算、などの加算単価もあります。
→ 認可保育園の補助金はいくら?設置基準と保育士の給料が低い仕組み
加算手当とは?
例えば、賃貸加算と取り上げてみましょう。
定員20名の場合は原則的に年間398.6万円が助成金として支給をされます。
このようにして算出をされる収入と、実支出(経費)額の少ない方が実際の助成金として支給をされることになります。
また、整備費についても、工事における対象経費の4分の3が助成されますね。
このように現在は手厚い支援がなされている企業主導型保育ですが、2017年度時点で地方での開設は非常に多くなっており、東京などの緊急性の高いエリアでの開発があまり進んでいないなどの問題も挙げられていますね。
企業主導型保育事業の利用対象者は?デメリットも多いは本当か?
 では、実際に企業主導型保育施設が始まった場合に、利用ができる人は誰になるのでしょうか?
では、実際に企業主導型保育施設が始まった場合に、利用ができる人は誰になるのでしょうか?
実際の企業主導型保育施設の場合は自社などの従業員が利用をする「従業員枠」のみで運営をすることも可能となりますが、地域住民も利用ができる「地域枠」を設けて運営をすることも可能です。
| 従業員枠 | 地域枠(設定は任意) |
| ・事業実施者の従業員児童
・事業実施者と利用枠契約を締結した子ども・子育て世帯の処出金を負担している事業主の従業員児童 (※椅子れも非正規雇用労働者も含む) (子ども、子育て支援法における保育認定は不要) |
・従業員枠対象外の子ども
(子ども子育て支援法における保育認定を受けたもの児童など) ※地域枠を設ける場合、総定員の50%以内 |
企業主導型の職員配置と基準
企業主導型の保育園の職員配置についても書いていきましょう。
保育従事者の配置はもちろんしなければなりません。
1,乳児おおむね3人に対して1人
2,満1歳以上満3歳にみたない幼児はおおむね6人につき1人
3,満3歳以上満4歳に満たない児童はおおむね20人につき1人
4,満4歳以上の自動はおおむね30人につき1人
ちなみに、保育士として従事をしている人がいる場合に大事なことは最低でも半数は保育士の資格を持っていることです。
保育の質の向上のために、保育士の割合が高くなる(75%、100%)なるほど補助単価が高くなります。
→ 保育士の配置基準の計算方法と緩和とは?認可と認可外の違い
ANAも保育園を導入
ちなみにここ2018年4月には子育て支援対策として、ANA(全日本空輸)が東京都大田区の羽田空港内に開園させた企業内保育所「‘OHANA ほいくえん はねだ」を作りました。
空港会社も人材確保が困難となっていることから確保に動いているようですので今後どうなるのか?目が離せないです。
ANAはこの夏にも保育園を作って人材確保のために動いていくようなので、これを皮切りにどんどん保育園ができてくれればと思います。
他にも不動産会社やアウトレットモール、イオングループなど小さな子供をつれて働いている女性の多い企業はこの企業主導型保育事業を取り入れて職員がより働きやすい福利厚生の目的から作る傾向にあります。
もちろん自社の資金は必要でも認可保育園並みの助成金もあるという点で人気ですね。
どこの企業でもつくれるのではなく審査などもありますので、これから作ろうと思っているのならば市区町村のホームページや管轄の保育課などに問い合わせてみましょう。
セブンイレブンが保育園を導入
イオンに続き、大手のコンビニチェーンであるセブンイレブンも企業主導型保育園を開園しました。
7月2日に企業主導型の「セブンなないろ保育園」を仙台市青葉区一番町のセブン-イレブン仙台柳町通店の2階に開園します。
セブンイレブンの社員はもちろん、加盟店の従業員や地域の住人を受け入れることにより働きやすい環境づくりに務めていきたいとコメントを残しています。
東北には初の保育園となっており、セブンイレブンとしても慢性的な人材不足の解消のために働きやすい環境作りは必須となってきていますね。
運営は保育園の運営に関する企業の中でも大手のアイグランが運営をすることになっています。
→ 保育サービス企業ランキング 市場規模はどれくらいあるの?
ちなみにセブンのなないろ保育園が作った仙台でも深刻な待機児童問題もある地域となっています。
4月1日現在、市内の保育施設の待機児童は138人で、大半が3歳未満となっていますのでより小さな子供を受け入れられる保育園は必要となっていますね。
企業主導型の場合は自社の職員の子供を預かることで働き手の確保もできますし、近隣の待機児童となっている人も預けることができるため社会貢献にもなりますのでより増得ていけばと思いますね。
企業主導型保育園のデメリット【保育士の確保が大変】
 補助金が認可園なみに出るというのは良い点なのですが、企業主導型保育園で気をつけなければならないデメリットもあります。
補助金が認可園なみに出るというのは良い点なのですが、企業主導型保育園で気をつけなければならないデメリットもあります。
まず園児を集めることになるのですが、認可保育園のように市区町村の自治体から園児を入れてもらえるわけではなく基本的には無認可保育園と同じように自分たちで集めなければなりません。
もちろん、入園をしている児童が多いほど補助金も大きくなりますし、収入の面でも入ってくるため園児の数は無認可保育園同様にシビアに大変となっています。
園児を自分たちで集めなければならない
また、企業主導型保育園の場合に難しいこととは「従業員枠」と呼ばれる会社の福利厚生のための施設でもあるため保育園を建設することにより最初から入園をしてくれる人を確保しておく必要がありますね。
企業主導型保育園の場合には従業員枠を一般枠が超えることはダメだといわれています。
そのためバランスをよく見て入園をさせなければなりませんが、一般枠は大事な収入源になります。
結果として集客をしなければならず、それが失敗をすると補助金もままならないため苦労をすることになりますね。
認可と同じ土地が見つかるか?
企業主導型保育園は限りなく認可に近い形となっており、建物自体も認可の基準を満たしているものになっている必要があります。
施設の広さ、保育士などの職員配置、給食設備、防災管理、衛生管理などいろいろな基準を満たしている物件を見つけることはかなり困難だと言われていますね。
まだ土地が余っている地域などは可能かもしれませんが、東京、大阪、名古屋、福岡など首都圏で人があふれかえっている地域では土地を探すことに苦労をします。
そのため、中には自社の土地の中につくってしまったという企業もあるほどですね。
初期投資がかかる
もちろん無料で開園をできるわけではなく、基本的には自己資金を投資して保育園を作ることになります。
そのため、物件(購入費、家賃)、家具、人材採用費、事務経費など規模にもよりますが費用は結構かかりますし、助成金だけでまかなうことは難しいので最初は初期投資も必要になりますね。
そのため、企業が企業主導型保育事業をしようという場合には収益が将来的に見込めるか?また、地域枠での入園希望者がどれくらいいるのかをしっかりと把握しなければなりません。
メリットとデメリットのまとめ
他にも企業主導型保育事業を行うメリットデメリットがありますので表にまとめてみましょう。
| メリット | デメリット | |
| 利用者 | ・開園時間に柔軟な対応をしてもらえる(24時間など)
・費用の負担が少ない。 ・施設によっては病児保育も可能。 ・職場近くに保育園があるため緊急の駆けつけ、授乳、休み時間へ様子を見に行ける。 ・従業員が優先的に入りやすい。 |
・保育園の立地が職場近くになるため場合によっては電車やバスなどで連れて行かなければならない。
・勤務が休みの日は利用しにくく自由度は低い。 ・園によっては行事が少ない。 ・環境が認可保育園と比較をすると見劣るケースもある。 ・園庭がない可能性もある。 |
| 企業 | ・企業の女性が働きやすい環境の1つになる。
・人材確保がしやすくなる。 ・子育てなどの理由の離職を減らすことができる。 ・企業イメージが良くなる。 |
・経営上の負担が増える。
(書類などの申請関係) (地域の保育園児の募集と契約) (保育士の確保)など
|
企業主導型保育事業の場合について、特に企業の福利厚生、人材確保の一環として非常にメリットのあるものだと思いますので、会社としてメリットも多い事業だといえます。
その代わり、保育という特殊な世界となるため運営や設置などに関しては経験のある人の採用など手間もかかることは間違いないのでその点の費用対効果などもよく比較をしてから導入を検討しましょう。
ただし、無認可保育園を開いて福利厚生の一環にしようという考えよりは補助金がでるという点でメリットもあります。
無認可保育園の運営は営業が間違いなく必要なので、運営をしていく点でも非常に大変です。
中には経営難で苦労をしている保育園もありますので注意をしましょう。
企業主導型保育を導入するメリット【会社の利益も増える?】
 これはなんといっても各企業も合わせても柔軟な保育サービスを提供することが可能になるという点です。
これはなんといっても各企業も合わせても柔軟な保育サービスを提供することが可能になるという点です。
小売、飲食、公共交通機関など、夜間や休日に働く従業員が多い企業では、それに対応した保育施設を設置できますのでその企業の希望に併せた保育施設を準備することが可能です。
また、認可保育園へは入園しにくい非正規社員や短時間勤務の社員についても入園ができるので対応がしやすいという点も大きなメリットです。
さらにメリットとしては複数企業が共同で保育施設を設置することなども可能という点です。
例えばA社とB社が一緒にお金を出し合って保育園として運営が可能になるという点です。
助成される整備費・運営費も認可施設並みとなっているので、中小企業でも保育園設置が可能となります。
保育園の設置までがスピーディー
認可保育所とは異なり、自治体の認可を必要とせず、認可外保育施設の設置について都道府県等に届け出た上で、助成申請を公益財団法人児童育成協会に行うことになりますし、認可保育園と比較をするとよりスピーディーに設置が可能になります。
企業主導型保育事業のおかげで柔軟性も生まれた保育園の設置が可能となります。
「育児休業制度などを活用できる」
「出産後も働くことができる職場環境を整備することが可能」
「企業の人材確保に役立つ」
「女性職員のが働きやすい環境を作れる」
こんな風になかなか参入をしにくい助成金のある保育園が設置をできるという点で大きな魅力のある保育形態であると思います。
助成金もあるということから、他の保育サービス会社の場合は開園時間などの自由が利かないなどのデメリットもありますので今後保育園を作ろうと思った場合には企業主導型保育施設はとても重要なポイントになってくるといえますね。
様々なポータルサイトもできていますし、市町村での説明会もありますので気になる方は一度聞きにいってみましょう。
なんといっても助成金があるのは大きなメリットといえますね。
会社にとってのメリット3選
会社が企業主導型保育を行ことによるメリットはいろいろとありますので紹介をしていきましょう。
1.従業員の離職を防ぎ、就労に応じたニーズに対応可能
企業も今は人材不足に時代で子育てにより離職をせざる負えない職員もいます。
また、短時間働きたいという人は保育園へ入園ができないため見てくれる人がいないと仕事もできないという結論になりますね。
そのような離職や短時間などの就労形態でも預ける先をして企業主導型の保育園を運営するメリットはありますし従業員への福利厚生の意味でもメリットのある方法となります。
2.地域の貢献につながる
保育園を作ることにより地域で預けたい子供を受け入れられますし、園庭があれば開放をすることにより貢献できる事業となりますし会社の名前を知ってもらうこともできます。
3.認可外保育でも補助金がもらえる
企業主導型保育園は無認可保育園という扱いになります。
すると通常は何の補助金もないのですが認可保育園と同水準の助成金が受けられるというメリットがありますので会社としても負担が少なく保育園を作ることが可能となります。
利用者のメリット3選
利用者には利用者にとってのメリットがありますので紹介をしていきましょう。
1.就労形態に応じた保育が可能
短時間でも、他の保育園では利用がしにくい時間帯でも利用が可能となりますので自由に働けるスタイルとなります。
子供の預け先に困ることもないため安心をして働けます。
また、中には会社の敷地内に作っている場所もあり送迎の手間もかからないケースもありますね。
2.職員や設備に規定があるため安心
無認可保育園と言っても職員の配置や施設の状況などは厳しい監査もありますので一定の水準が保たれているため安心できます。
3.費用の負担も少ない
まず企業主導型保育の場合には企業が十分な助成金や補助を受けられるため内部の職員の子供を預かる際には認可と同等の料金で利用が可能となるでしょう。
保育士のメリット5選
会社にも利用者にもメリットはあるのですが、実は保育士にもメリットがありますのでまとめて紹介をしていきましょう。
1.運営母体が大きいと待遇も良くなる
これはもちろん企業主導型保育を運営している母体の規模のよりますが、待遇面認可並みになるかそれ以上の待遇が期待できる場合もあります。
また、企業内のある保育園なので土日祝日が休みなど就労がしやすい環境のケースもありますので続けて働きやすい環境が魅力ですが母体の考えによってことなります。
2.会社が通勤に便利な場所にある
会社の中に作ったり、近くに作ることから通勤は便利な首都圏になる場合もあります。
3.新設のオープニングが多い
今企業主導型保育というのはニーズがあり、どんどん新設で作られています。
そのため、新しい新規の保育園で働きたいという方にはチャンスが多いですし、管理職や主任などを目指している方は経験があればなれるチャンスも多いです。
4.保護者が近くにいるため緊急の場合でも対応してもらいやすい
保護者が預けていますが会社内などのケースもあります。
すると、発熱など緊急な状況でもお迎えに来てもらいやすく連絡もすぐに取れますので対応をしてもらいやすいですし、子育てに関して理解も多い会社の可能性が高いです。
5.少人数の保育になる場合もある
企業主導型保育の場合は多くの人数を預かるようなケースは少なく、どちらかといえば小規模なところが多いです。
そのため、少人数できめ細やかな保育をしたい方には最適な保育園となる場合もあります。
企業主導型保育事業の問題点!補助金詐欺も多い最悪な現実
 企業主導型保育事業のメリットはすぐに認可保育園を作れる点です。
企業主導型保育事業のメリットはすぐに認可保育園を作れる点です。
新規参入をする側からすると、補助金がもらえ、短い期間で認可保育園を開園できるという点は大きなメリットですね。
しかし、補助金と言う点を狙った詐欺や問題も多いのがこの企業主導型保育事業です。
その理由について書いていきましょう。
詐欺も多い企業主導型保育施設
企業主導型保育施設ですが、ここ最近補助金も認可保育園並みにでることから多くの会社や企業が参入をしています。
しかし、この企業主導型の保育事業に対して不正に補助金を受給している人も多いようで問題になっていますね。
例えば、関西は東京などに保育園を運営している法人が企業主導型保育園を運営していました。
その法人は既存の認可外保育園の園児と保育士を新施設に移管させつつも、「もぬけの殻」状態の旧施設を一定期間存続させることで、企業主導型保育施設を新設したかのように見せて助成金を受け取っていたというものです。
結果的に看板はあるけれども中には誰もいないという状況になったことから発覚しましたがこんな風な不正受給が行われるとせっかくの企業主導型保育園という事業もなくなってしまう可能性もありますのできちんと運営をしてほしいものです。
不正受給が問題の企業主導型保育園
もちろんメリットの多い企業主導型保育園になりますが、問題も多いのは正直なところになります。
例えば、西日本で保育会社を運営している企業が東京へ保育園を作るために参入をしたのですが給与の未払いなどにより結果的には保育士は全員退職することになりました。
この問題として明るみでたのは保育園の経営者の経営能力の低さという問題とそれを見抜くことができなかった問題があるということになります。
もちろん企業主導型保育園のメリットは助成金が認可保育園並みにもらえるということなのですが、運営者はある程度の自己資金も必要となりますし初回の助成金を支払われるまでに運用資金も必要になりますね。
しかし、その資金を目当てにしている経営のずさんな状況もありますので精査をすることが1つの問題となっています。
また、この本来企業主導型保育園は2016年4月1日以降に新たに園を開設した場合のみ。既存の保育園を廃止して新園に振り替えた場合や、園を移転、建て替えた場合は対象にならないためお金の返還を求める場合もあるという決まりもあります。
それに対して、この株式会社は一定期間運営をしてないもぬけの殻の状態の建物を運営していると偽り不正に受給をしているというケースもありますね。
結果的には数千万円の不正受給も多くなってしまっている状況もあるため問題になっており不正受給の疑いはぬぐえないですが結果的にはわからないというのが正直なところです。
行政の調査の甘さが明るみになっているのですが、行政としては1つでも保育園を運営して待機児童の解消をしたいという思いがありますのでなかなか入りこめていないのも正直なところ。
企業主導型の助成金は非常に魅力的なのですが不正受給が多いという問題も明るみになっているているのは正直なところですね。
不正受給ではないですが、保育士の処遇改善手当も同じような感じになっているのでなんとかならないものかと思います。
中小企業も導入を検討
また、ここ最近は中小企業の企業型保育事業の参入を検討しています。
日本商工会議所と東京商工会議所で積極的に説明会を行っているのですが、多くは中小企業の経営者になっています。
その理由としては「深刻な人材不足」だからです。
中小企業の大きな働き手となっている女性ですが、子供が生まれると同時に退社をしたり、待機児童の多い地域になると子供を預ける先がないため仕方なく退社を申し出る女子社員も多いからです。
人材不足の離職を防ぐためには自社で保育園を作って社員やパートの子供を預かることが何よりも近道という考えになることから企業主型保育事業の参入を検討する中小企業が多くなっています。
はやり認可並みの補助金と運営ができるという点は大きな魅力。
今後も企業主導型保育事業が広がっていくでしょうし、今後は会社の中は企業内保育園を作るとなった場合にはスタンダードな考えが企業主導型保育事業のなるかなと思いますね。
企業主導型保育事業のまとめ【メリットデメリットを理解しよう】
 企業主導型保育園は企業の福利厚生や社員が働きやすい環境を作ること、また地域に根付いた保育園を作る事業となっています。
企業主導型保育園は企業の福利厚生や社員が働きやすい環境を作ること、また地域に根付いた保育園を作る事業となっています。
しかし、安易に補助金がでる、助成金が出るからといって手を出すことはあまりおすすめしません。
今会社にとって必要なのは、事業所内保育園なのか?それとも企業主導型保育園なのか?無認可保育園なのか?託児所なのか?そのあたりもよく考えて企業主導型保育園へ参入をすべきだと思いますね。
ただし、この直近で保育園を作るのならば企業主導型保育園が補助金などをトータル的に考えた場合に間違いなく一番良い方法ですね。
これがいつまで続くかはわかりませんが企業主導型が基本となっている間に企業は設置を検討しましょう。
人気記事 → 保育士転職サイトランキング!おすすめ22社を徹底比較【口コミ評判】
人気記事 → 保育士バンクの口コミ評判!特徴8選と登録の方法 退会はしつこい?

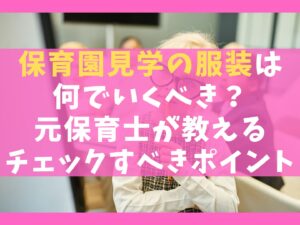
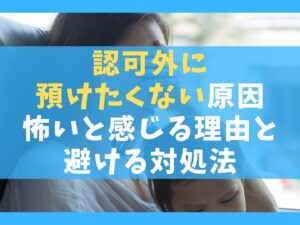
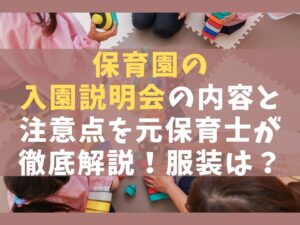
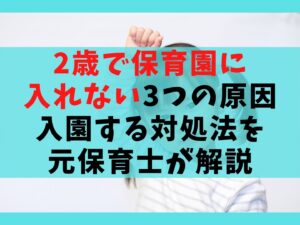
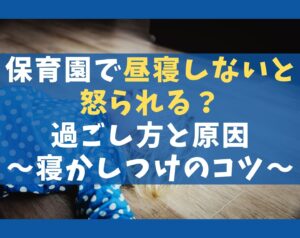
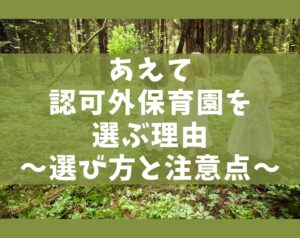
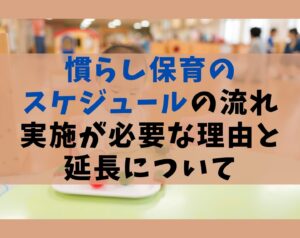
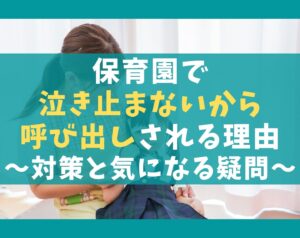
コメント
コメント一覧 (14件)
[…] 関連記事→企業が保育園を作るなら企業主導型保育事業で助成金を手に入れよう […]
[…] 関連記事→企業が保育園を作るなら企業主導型保育事業で助成金を手に入れよう […]
[…] 関連記事→企業が保育園を作るなら企業主導型保育事業で助成金を手に入れよう […]
[…] 関連記事→企業主導型保育事業とは?保育料金の助成金が出るって本当? […]
[…] 関連記事→企業が保育園を作るなら企業主導型保育事業で助成金を手に入れよう […]
[…] […]
[…] 関連記事→企業が保育園を作るなら企業主導型保育事業で助成金を手に入れよう […]
[…] […]
[…] […]
[…] 企業主導型の保育園となると、その企業である会社の考えに左右をされることから開園時間はさらに伸びていく可能性もあると考えれれており、先日企業主導型の保育園の方にお聞きすると、朝の7:00~夜の23:00まで開園をしているとのことでした。 […]
[…] 選択肢としては認可外保育園、企業主導型保育園、地域主導型保育事業のいずれかはありますが、補助金や助成金の入らないため認可外保育園は、その園がよほどの独自性や価値がないと経営は厳しくなっていく一方になります。 […]
[…] 預ける人からすると企業主導型保育園へなってくれることで補助金でるので保育料も安くなったり外部の子供を預かる場合もあるのでお友達も増えるというメリットがあったりしますね。 […]
[…] そのほかにも保育ママと呼ばれる満3歳未満を預かる形態の保育園や幼稚園、認定子ども園、企業主導型保育園などが主な保育園の形態となっています。 […]
[…] 最近は認可保育園以外にも企業主導型保育園や認証保育園など様々な形態の保育園が出てきており、そこでも認可並みの設備と環境が整っている場合もあります。 […]