赤ちゃんがミルクを飲まないという悩みは多いです。
私が保育士として乳児のクラスを見ているときに、ママ達から多い悩みは「ミルクを飲んでくれない」でした。
ミルクを飲まない体重も増えませんし「もしかして病気?」「何は異変が起こっているの?」と心配になってしまうため多い悩みであったといえます。
この記事では赤ちゃんがミルクを飲まない時の原因や理由、対処法がわかります。
赤ちゃんがミルクを飲まない原因と理由5選【まずはチェックしてみよう】
もちろん赤ちゃんによっては気分的にただ飲みたくないだけなんてこともありますが、ミルクを飲まないことが続くと心配です。
はいミルク飲まないー!
乳30しか出てないのミルク100しか飲まないー!
絶対足りてねぇだろー😊— えん®4m♀元切迫 (@16w29938123) May 23, 2020
赤ちゃんミルクも飲まないしフォローアップミルクもほとんど飲まないんだけど栄養大丈夫かしら………
— ゆいこ (@inb0rders) January 28, 2019
こんな風に心配になってしまいますし、体重も思うように増えていないと何らかも問題があると考えるのが普通です。
そこで、赤ちゃんがミルクを飲まない原因と理由を5つ書いてみました。
| 1.ミルクを飲まない原因は哺乳瓶の乳首が苦手
2.ミルクの味が合わない【粉ミルクのメーカーを変える】 3.ミルクの温度!飲まない・飲みが悪い時はチェック 4.環境が落ち着かない 5.病気の可能性あり!すぐに病院受診 |
1.ミルクを飲まない原因は哺乳瓶の乳首が苦手
母乳ならばそんな問題もないのですが、哺乳瓶だとこの問題が一番多いです。
それは「哺乳瓶に着ける乳首」です。
乳首はすべて同じと思っている方もいるのですが、メーカーや会社によって形は異なっており穴の年齢によって大きさは異なりますので赤ちゃんの好みのものにしてあげましょう。
よくあるのが今まで飲んでいた乳首から新しい乳首に替えたタイミングで急に飲まなくなったり、同じメーカーだけれども形を変えたなど。
赤ちゃんの口の中はとにかく敏感で些細な形の変化も感じ取る力をもっていますので注意をしましょう。
相性の悪い乳首にするとミルクを飲んでいるつもりが空気も一緒にお腹の中に入っていき赤ちゃんのお腹が張ってしまったり、げっぷばかりでてしまって赤ちゃんも疲れてしまいます。
乳首があわないときの対策
もし乳首が合わないという際にはまず交換をしてみましょう。
交換をしたのならば元の形に戻してもよいですし、普段は母乳でミルクを飲んでいる赤ちゃんがお白湯やお茶などを哺乳瓶で飲ませるとほぼ飲みません。
私も娘は2人も母乳で育ったので哺乳瓶は一切受け付けませんでしたのでお母さんのおっぱいに慣れているとあまり飲んでくれません。
それでも乳首で吸ってくれない場合にはスプーンで飲ませるなどの対応に替えてみて下さい。
月齢も上がってきているのならばコップに変更をしても良いですね。
2.ミルクの味が合わない【粉ミルクのメーカーを変える】
次に多いのが「味」です。
ミルクを作るとなるといろいろな粉ミルクが販売をされていますので、単純に赤ちゃんに合わない味のミルクを提供しているだけかもしれません。
それならば味を変えてみるというのも一つですが、1缶を購入すると飲まなかったときにもったいないのでキューブ型など小さなサイズのものから試してみましょう。
特に母乳と粉ミルクを併用していると母乳は飲んでくれるけれども、粉ミルクはあんまり飲んでくれないというケースはとても多いですので混合の場合はいろいろと試して飲むものを赤ちゃんに選んであげましょう。
私は保育学校で粉ミルクの作る実習がありました。
その際にいろいろな味見をするんですよね。
ほほえみ、はぐくみ、すこやかなどいろいろとありますがほほえみは甘めなど大人が飲んでも味の違いが分かるほどメーカーによってことなります。
赤ちゃんも生後3ヶ月を向かえる頃のは味の違いも分かってくるといわれていますので様子を見て味を変えないにしましょう。
そして、いろいろと試して赤ちゃんの好みの味を見つけてあげて下さい。
ミルクが濃い(薄い)
また、保育園でもミルクを飲ませているときに飲まないことが多いのは「濃さ」になります。
もちろん栄養的には規定量で作るべきなのですが、赤ちゃんのよっては「濃いミルクが好き」という赤ちゃんもいれば「薄い味が好き」と個人差がありますので濃度を少し調整してみると飲むようになることもあります。
→ 粉ミルクランキングはほほえみがおすすめ?成分を比較評価してみた
母乳を飲まないはどうすべき?
もちろん中には母乳を飲まない赤ちゃんもいるでしょう。
飲まない原因として考えられるのは「母乳の味が違う」と言う点が多いです。
母乳はママが食べたものが血液をして出てくるため、揚げ物をたくさん食べた、甘いお菓子やケーキを食べた、ファストフードやジャンクフードを食べたなど赤ちゃんにとって違和感がある時です。
そんな時はママが食べるものを変えてみる、粉ミルクを一度飲ませてみるなどの対策をしましょう。
3.ミルクの温度!飲まない・飲みが悪い時はチェック
ミルクを作ったことがある人ならばわかるのですが、温度のチェックの基本はミルクを一滴自分の腕などに垂らして熱くないか?ぬるくないか?などをチェックすることになります。
その際に適度な温度というものがあります。
(やや熱めの40°が最適温度です)
しかし、人肌というのはあくまでも目安で赤ちゃんによって個人差があるのは正直なところ。
そこで、ぬるめや熱めなど好みの温度にしてあげてください。
例えば、暑い夏の時期に熱めのミルクを作っても飲まなかったりすることもあるようですので、赤ちゃんの様子をみて一番飲みやすい温度を覚えるようにしましょう。
なかなか感覚では難しいですが、保育園で0歳児に担任になると調乳係と呼ばれるミルクを作るだけの専門になる日もありました。
その際に保育園で赤ちゃん一人一人が飲みやすいように「好みの温度表」なるものを作っていましたし、担任になると1ヶ月もすればその赤ちゃんの好みの温度もわかりますのでよいですね。
4.環境が落ち着かない【ミルクを集中して飲めない】
赤ちゃんがミルクを飲む際には大人と一緒で落ち着く場所を好みます。
大人も一緒で騒がしいカフェと、静かな落ち着いたカフェとどちらがゆっくりとコーヒーを飲むことができますか?
それはもちろん「静かなカフェ」ですよね。
これは赤ちゃんも同じでテレビを着けたり、スマホをいじったりしたまま赤ちゃんの飲ませても赤ちゃんはどことなく落ち着きません。
静かな環境でミルクを飲ませるようにしてあげてください。
また、ママも忙しいのはわかるのですが赤ちゃんの目をみて飲ませてあげて安心感を与えましょう。
赤ちゃんにとってミルクは大事な食事です。
食事の際にスマホをいじっていると注意をするのと同じことなので目を見て安心感を与えてあげてくださいね。
室温と明かりをチェック
あとは室温もチェックをしましょう。
暑い夏に暑い部屋でミルクを飲めませんし、部屋が寒い時にミルクを落ち着いて飲むことはできません。
そのためにも落ち着いてミルクを飲むためには、部屋の温度を適温にしてあげること、そして室内の明かりにも配慮をしましょう。
明るすぎると落ち着きませんし、暗すぎても落ち着きませんので適度は明るさにすることです。
| 赤ちゃんにとって快適な温度と湿度は、室温20~25℃(湿度50-60%)です。
(参考:東京都福祉保健局「健康・快適居住環境の指針(平成28年度改訂版)」) |
5.病気の可能性あり!すぐに病院受診【ミルクを飲まないときの様子と行動】
ここまで赤ちゃんがミルクを飲まない時の原因について書いてきました。
しかし、ここで書いていることをすべてしてもうまくいかなかった時や以下のような行動が見られた時は、すぐに病院へ受診をすべきです。
子供がお熱~😭
しんどさでミルク飲まないし、心配ー😭🥺 pic.twitter.com/ztskBFU8KJ— ℍ𝕚𝕟𝕒 (@Hina_nas) December 10, 2020
まずはかかつけの小児科などの病院へいきましょう。
| ・数日排便がなく便秘で、お腹が膨れて固くなり、機嫌が悪い
・激しく吐く機嫌も悪い ・時間に関係なく原因不明で激しく泣きじゃくる ・便の色が白かったり、イチゴジャムのようだったりといつもと違う ・おしっこの回数が普段を比べて少ない(量もチェック) ・鼻づまりや発熱などの風邪症状がみられる |
機嫌が良かったりニコニコとしている場合にはあまり心配もしなくても大丈夫なので、いったん様子を見ましょう。
飲まないときには体重をこまめにチェックしてみてください。
ミルクを飲まない時の対策と対処法5選【新生児もチェック】
 次に赤ちゃんがミルクをなかなか飲んでくれない時の対処法について書いていきましょう。
次に赤ちゃんがミルクをなかなか飲んでくれない時の対処法について書いていきましょう。
もちろんいろいろな方法がありますが、元保育士としていろいろな赤ちゃんとかかわってきた中で実践をしてきた方法になります。
ただし、個人差がありうまくいく場合もあればうまくいかないことも。
そして昨日はうまくいったのに今日はダメということもありますので、いろいろとチャレンジしてみましょう。
| 1.散歩へ出かけて遊ぶ【飲みが悪い時も】
2.時間を変えてチャレンジする 3.ミルク以外の飲み物にかえてみる 4.場所をかえてみる【環境は静かな状態に】 5.ミルクを飲まないときはあきらめる |
1.散歩へ出かけて遊ぶ【飲みが悪い時も】
まずミルクを飲まない原因としてはお腹が空いていない可能性もあります。
これは大人も子供も同じなのですが、外で思いきり遊んだあとに食事をするとモリモリとご飯を食べることができますが雨の日で一日家の中にいたりどこへも出かけられない場合にはお腹もすかないもの。
これは赤ちゃんも同じで活動量が多いとお腹もすいて良く飲んでくれることも多いです。
保育園でも月齢によって異なりますが、小さな赤ちゃんの場合には日光浴や抱っこをして周辺を歩いて散歩するだけでも気分転換になりますし、赤ちゃんは疲れてしまうもの。
すると驚くほどミルクを飲んでくれることもありますので外へ出かけて日光浴をさせるという方法はありです。
また、地域の保育園に言ったり、市区町村にある遊び場みたいなところへ行って遊ぶのも良いと思います。
家だけではなく外へ出かけていろいろな刺激をうけるとお腹もすきやすくなりますよ。
2.時間を変えてチャレンジする
もしなかなか飲んでくれないならば時間を変えてみましょう。
するといきなり飲んだりすることはよくあります。
大人でも「あんまり食欲がわかない」という時間があるものでこれは赤ちゃんも同じです。
飲まないときは「たまたま飲みたくないだけ」ということもありますので様子をみてのませるようにしてみましょう。
保育園でも多いのですが「眠たくてミルクをのむどころではない」「うんちがでそうでお腹が張っている」などの理由からなかなかミルクを飲まない時もあります。
その場合に30分~1時間くらい時間をあけてみると、驚くほどすっとミルクを飲む場合もありますのでチェックをしてみましょう。
3.ミルク以外の飲み物にかえてみる
それならば中身をミルクではなく、お白湯やお茶、果汁などに替えてみると良いです。
ミルクを飲んでくれないけれども他の味ならば飲んでくれるということはよくあることです。
そのため、赤ちゃんの様子をみて飲ませるようにしてみてください。
味が変わると赤ちゃんも急に飲んだりするものですので、赤ちゃんの様子をみて中身を変えてみても良いでしょう。
ただし、新生児はお白湯も果汁も避けておきましょう。
まだ、飲ませるには早く、お腹を下したり、ミルクを飲まなくなってしまう可能性もあります。
→ 新生児に白湯はだめ?赤ちゃんにいつから?【湯冷ましの作り方と量】
4.場所をかえてみる【環境は静かな状態に】
なかなかミルクを飲んでくれない。
それならば場所を変えてみると飲んでくれるかもしれません。
自宅ならば部屋を変えてみる、たまにはママがソファに座ってミルクを飲ませてみるなどいつもと違った環境に替えてみると赤ちゃんも飲んでくれることもあります。
環境が変わると雰囲気も変わり意外と効果的。
保育園でも場所を変えると飲んでくれるケースもあり、室内でミルクを飲ませるようにすると飲まないのでちょっとだけ廊下を散歩してから飲ませると驚くほど飲んでくれるということもあります。
たまには場所を変えてみると飲んでくれるケースもありますね。
5.ミルクを飲まないときはあきらめる
なかなかミルクを飲んでくれない。
どうすれば飲んでくれるだろう、なんで飲んでくれないのだろう。
赤ちゃんがミルクを飲まないとどうしても不安になってしまうこともありますが、そんな時に悩んだりするとママもイライラしてしまい悪循環になります。
それならばいっそのこと「あきらめましょう」。
飲まない時はいくら頑張らせても飲まないですし、赤ちゃんも飲む気がないので飲みません。
潔くあきらめてタイミングをみてあとでミルクを飲ませると飲んでくれることもあります。
→ 新生児と赤ちゃんのミルクの量は?月齢別の目安量と判断のポイント
赤ちゃんがミルクを飲まないときまとめ【長いときは病気の可能性ありなので受診を】
 赤ちゃんはミルクを飲まないときの原因と対処法について書いてきました。
赤ちゃんはミルクを飲まないときの原因と対処法について書いてきました。
結論としては赤ちゃんだって大人と一緒でミルクを飲むときもあれば、あまり飲まない時もあるということです。
もちろん飲まないことが続いているのならば病院へ受診をするなどの対応はすべきですが、一回だけ飲まないという場合にはそこまで心配はいりません。
ミルクを飲まないときにはそのままではダメなので何らかの変化をさせることが大事です。
環境を変えるのか?ミルクの温度や中身を変えるなどをしてみるとよいかもしれませんし、その時は一旦あきらめるというのも1つですのでママがイライラしないこと。
そしてミルクを飲んでくれないと思いつめないことは大事ですよ。
体重をみて機嫌がよいのならば赤ちゃんは気分的の飲まないだけなので、気分を切り替えていっしょに思いきり遊んでみたりして様子をよく見るようにしてみましょう。
人気記事 → ウォーターサーバーは赤ちゃんにいつから?子育て世代のおすすめ3選
人気記事 → ミキハウスの幼児教室は体験がおすすめ!特徴と月謝と口コミ評判




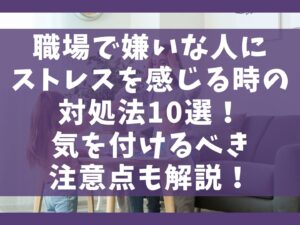
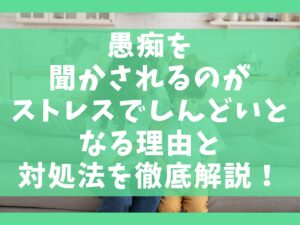
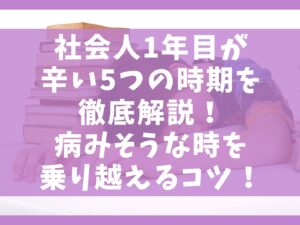
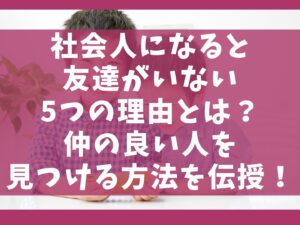
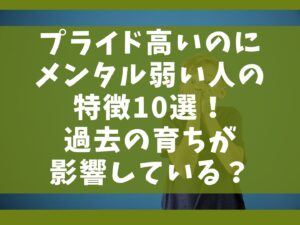
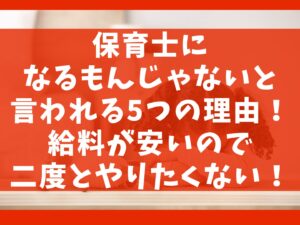
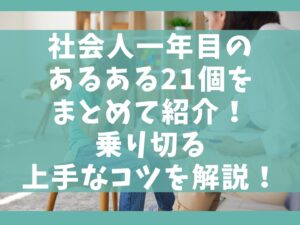
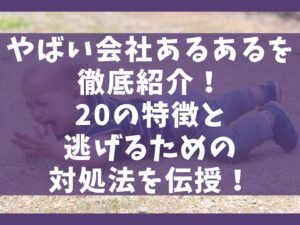
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 2018年 11月 25日 トラックバック:赤ちゃんがミルクを飲まない原因と理由はなに?飲むようになる対策5選 | … […]
[…] 寝ない、ミルクを飲まないということもそこに当てはまりますね。 […]