慣らし保育の期間とスケジュールはどんな感じでしょうか?
保育園へ入ると、必ず慣らし保育というものがあります。
これは、保育園へ慣れるための保育のことで「慣らし期間」をして保育園へ預ける方法です。
この記事では慣らし保育の期間とスケジュール、慣らし保育を行う理由と気になる疑問に答えていきます。
慣らし保育の期間はどれくらい?スケジュールも紹介【1~2週間が定番】

慣らし保育はほとんどの保育園で行っています。
認可では、特に最初の2週間は推奨をされており、預かる子供のことも考えて配慮がなされています。
もう来週から慣らし保育かー。あー。慣れるかなー
— iwa02 ⛩ (@iwates) June 22, 2020
うちの坊ちゃんは今日から慣らし保育スタート。楽しかったみたいでよかった!
— クリアビジョン 牧内慶太 (@keita_makiuchi) June 22, 2020
慣らし保育については、保護者も不安に感じていることが多いですね。
期間は平均1週間~2週間ではあります。
そこで、まずはどのようなスケジュールで行われるのか?乳児と幼児別に紹介をしていきます。
乳児クラスの慣らし保育スケジュール【0・1・2歳児の最初は短め】
乳児クラスは慣らし保育があります。
特に小さな子供なので、慣れるまで期間が必要という理由もありますね。
園によって1~2週間程度は慣らし保育に最低でも期間がかかると思っておきましょう。
| 日程 | 子供の活動 |
| 1~3日目 | 1~2時間(30分ずつ増やす) ・ミルクを飲む(0歳児) ・おやつを食べる(1、2歳児) |
| 4~7日目 | ・ミルクを飲む、離乳食を食べる(0歳児) ・お昼寝前まで過ごす(0歳児) ・昼食を食べる(1,2歳児) |
| 8~10日目 | お昼寝をしておやつまで |
| 11日目以降 | 子供に問題がなければ16時や17時など時間が伸びていきます。 保育時間内の保育に2週間を超えたあたりで切り替わります。 |
赤ちゃんのクラスだと、場合によっては延長になる場合もありますので注意をしましょう。
ミルクが飲めない、食事がとれないなど命に関わる場合には延長となる可能性が高いですね。
幼児クラスの慣らし保育スケジュール【3・4・5歳児】
次に幼児クラス。
いわゆる年少から年長のクラスになります。
| 日程 | 子供の活動 |
| 1~2日目 | 午前中 |
| 3日目 | お昼ご飯終了まで |
| 4日目 | おやつまで |
| 5日目 | 夕方まで |
| 6日目以降 | 子供に問題がなければ通常通り |
幼児クラスは、子供の様子次第です。
もともと幼稚園へ行っていた、保育園へ行っていたという場合や全く問題なく過ごせる場合は3日程度で終えることもあります。
子供のようす次第で短縮をされる可能性もありますね。
登園1週間の突然の死亡が最多【予防のための慣らし保育は必要】
実は登園1週間の突然死が一番多いです。
これは、子供に過度なストレスがかかるため。
いきなり知らない人に預けられ、知らない人と遊んでとなると、大人でもすごいストレスがかかります。
主な原因は不明な点もありますが、過度なストレスが突然死を招く可能性もありますので、慣らし保育を実施する理由があるのです。
できれば、長い期間をかけてゆっくりと慣らして行くことが理想だといえますね。
慣らし保育を保育園が行う目的と3つの必要な理由【機関とスケジュールが大事】

慣らし保育を保育園が行う目的は主に3つあります。
今月、午前保育3回、昼食まで保育3回の6回しか保育園行けてないwww
育休中に慣らし保育必要な理由が分かったわ…— せの🍑1y(6/8) (@chi_sanasekai) May 19, 2021
慣らし保育は絶対必要
精神的な理由でも— ななこ (@nanaconacco) March 14, 2018
| 1.子供のことを保育士が把握する 2.保護者が預けることに慣れる 3.子供のことを観察するため |
詳細について、書いていきましょう。
1.保育士が子供のことを把握する【子供が環境に慣れる】
まずは、保育士が子供のことを把握するために実施します。
保育士はプロでもいきなり預かった子供のことを見極められるかといわれると、難しいです。
そのため、慣らし保育で子供の生活面、性格、体調、好きな遊びなどを把握します。
一週間くらい子供と接すれば、子供ことがわかるようになりますので、慣らし保育として意味があるのです。
2.保護者が子供と離れることに慣れる【環境を知る】
保護者が子供と離れることに慣れる意味もあります。
うっかり、0歳児保育園かわいそう、って言うツイートを読み込んでしまった…
娘がかわいくてしょうがなくて、離れたくない、けど、キャリアのために復職した身としては、なかなかこたえる。慣らし保育の当初、娘を預ける時も帰り道も、いつもの笑顔じゃなくて、硬い表情をしていた時は、本当に↓
— imperfect®︎WM w / 0y7m babygirl (@imperfect_1000) June 22, 2020
こんな風に、なかなか子供と離れられない保護者もたくさんいますね。
しかし、これは当たり前のことですので、ママも子離れをしてもらう意味で慣らし保育があります。
ママ達も心配になりますが、プロの保育士に任せるべきですね。
3.保育園も子供に問題がないかを確認するため【保育士も見たい】
保育園も子供に問題がないかを確認します。
例えば、健常児であるかどうか、子供自身の発達の問題などです。
この辺りはしっかりと見ており、保育園も子供に問題がないかを見極める必要があります。
保育園としても、新規入園の子供の性格などを見極める必要があるのです。
慣らし保育は期間を延長する場合もあり【入園後のスケジュールは最大何日?】

慣らし保育の期間は基本は3日~2週間です。
しかし、子供のようす次第では延長になる場合もありますので、注意をしなければなりません。
慣らし保育延長戦、今日は15時お迎え。先生に「お母さんお仕事は…?」
と聞かれ今週は調整できるようにしてると伝えたら、木金は16時迎えでと。
いいんだけど、元々17時まで預ける予定だから、その1時間の差意味あるのかなあ。慣らしの延長が必要な理由を言われなかったからちょっともやり— さや師_2y (@harushi_mama) April 14, 2021
また、市区町村によっては2週間~1ヶ月程度みる場合もありますので、保育園に従いましょう。
そんな慣らし保育ですが、場合によっては伸びる場合がありますので、その理由について書いていきます。
| ・慣らし保育中に熱を出して登園できなかった ・ミルク全く飲めず水分が取れない ・泣き叫んで落ち着くことがなく生活にならない |
慣らし保育中に熱を出して登園できなかった
慣らし保育期間中に熱を出したり、体調不良で欠席をした場合には園長になります。
例えば、5日間の慣らし保育期間があった場合は、5日間を消化して、はじめて通常の登園が可能です。
しかし、発熱や体調不良により登園ができないとなると、慣らし保育は終わっていません。
そのため、期間は延長となるケースがほとんどです。
ミルク全く飲めず水分が取れない
ミルクが全く飲めない赤ちゃんは慣らし保育が延長になります。
娘は哺乳瓶拒否が酷いので慣らし保育も延長かな。。。
— ゆずり@2y&5mの母 (@9vSRTQqvtWTKNzS) June 22, 2020
理由は「命に関わる」ためです。
中には母乳で育ってきた赤ちゃんが、いきなり哺乳瓶になってしまうということもあります。
そうなると、赤ちゃんはただでさえ知らない人達に拒否をしているのに、さらに水分も取れないということになります。
あまりにも危険があるため、最悪ミルクが飲めるようになるまで延長になることもあります。
泣き叫んで落ち着くことがなく生活にならない
赤ちゃんなど初めての集団生活になると、ママから離れるだけでも大泣きの場合も。
そんなときは落ち着くまで伸びるケースも稀にあります。
何よりも、子供が落ち着いて保育園に通えることが一番ですので、伸びることを覚悟しておきましょう。
慣らし保育のスケジュール気になる疑問【仕事が休めない・延長もある?】

慣らし保育の気になる疑問と質問に答えていきます。
はじめて保育園へ預けるとなると、不安な点も多いですよね。
ママ達も保育士もはじめての子供に対しては不安になることがありますので、気を付けるべきです。
仕事復帰で休めないけど慣らし保育はどうする?【できない時の対処法】
仕事がどうしても休めない時は、どうすべきでしょうか?
中には育休復帰のために、仕事を休めないという現状もありますね。
しかし、子供のことを考えると、いきなり長い期間あずけるというのはリスクがあります。
そんな時は以下の対処法を参考にしてください。
| ・祖父母や親戚など誰かにお迎えに行ってもらう。 ・パパにお願いをしてみる。 ・お迎えのベビーシッターをお願いする。 ・保育園へどうしても難しいことを相談してみる |
この辺りになるかと思います。
どうしても難しくても、保育園は子供の最善の利益を考慮しますので、よく考えましょう。
慣らし保育で泣くけど大丈夫?【育休中もあり】
慣らし保育で泣くことが心配。
これは当たり前です。
子供にとっては初めての環境で、いきなり知らない人に預けられたら泣きます。
泣いて当たり前と思っておきましょう。
また、育休中でも復帰へ向けて徐々に慣らしておきましょうね。
慣らし保育中の過ごし方に迷う【母親の疑問】
慣らし保育の期間はママも練習です。
今までそばにいた子供が急にいなくなると、困ってしまいますよね。
そんな時は一人の時間を楽しみましょう。
カフェでゆっくりとしてみる、仕事へいく準備を整える、出かけてみるなどです。
子供がいなくなった分、自由にできますね。
職場復帰までは一人の時間を楽しんでください。
慣らし保育へ行って夜泣きがスゴイ【理由を教えて】
これは、子供にとって過度なストレスがかかっているためです。
慣らし保育は子供にとってはすごくストレスがかかります。
そのため、夜に泣く夜泣きが起こることもあります。
慣れるまではしばらく続きますが、次第に落ち着いてくるでしょう。
コロナで入園が遅れても慣らし保育はあるの?
コロナなど、感染症や何らかの理由で入園が遅れた場合。
慣らし保育はあるのでしょうか?
今週から新一年生も月金授業スタート。学童も行きたくないと毎回半ベソ。次男も7月から保育園行けるのか?慣らし保育始めからやり直しだ。
そんなところに7月から夫が週3日出向で不在になると判明。
追打ちをかけて7月半ばから給食室改装工事するから3ヶ月間お弁当もってこいってさ!夏場のおべんと!— akiash (@akinimo) June 22, 2020
これについては、通常で慣らし保育が行われます。
遅れても入園が開始した時期から、慣らし保育は開始しますので、理解をしておきましょう。
短時間保育でも慣らし保育は必要?
短時間保育でも慣らし保育は必要です。
スケジュールは普通通り進んでいきますね。
あとは、先生と相談をして時間を延ばしていきましょう。
慣らし保育の期間とスケジュールのまとめ【保育園に慣れさせる期間】

慣らし保育の期間とスケジュールについて書いてきました。
期間は3日~1週間程度が基本です。
しかし、場合によっては延長もあり得ますので、子供の様子次第ですね。
何よりも子供にとってストレスのないようにするために、慣らし保育があります。
慣れればあとは安心をして預けられますので、子供も保護者も慣れるための期間とおもって慣らし保育を楽しみましょう。
人気記事 → 子供の青汁ランキングおすすめ3選と効果【幼児向け美味しい飲み方】
人気記事 → 子供の身長を伸ばす方法4選とサプリを紹介!年齢別の平均目安と遺伝
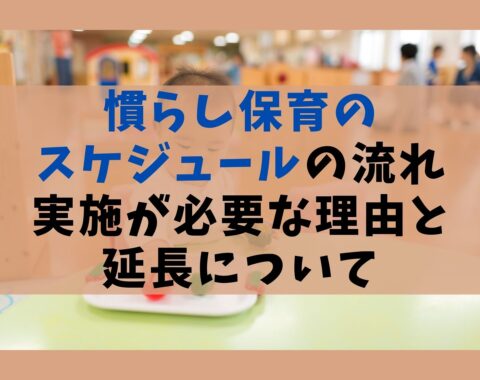
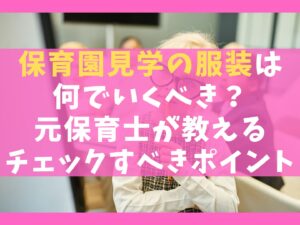
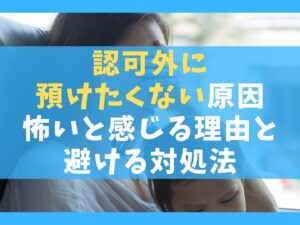
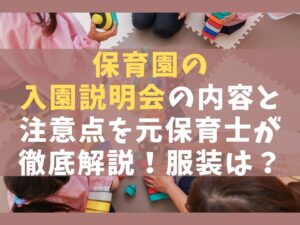
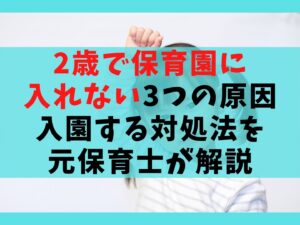
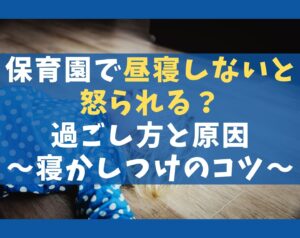
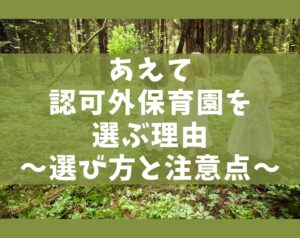
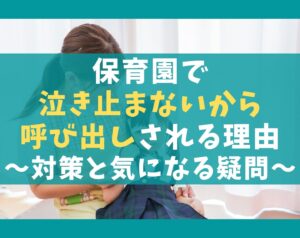

コメント